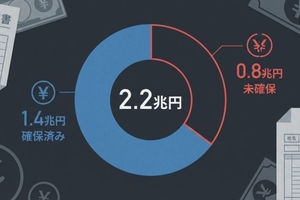「雑草」と呼ばれてきた草たち。本当に“邪魔な存在”なのでしょうか?
土壌・環境・人との関係から、草の役割と私たちの暮らしを見つめ直します。
私たちは近代的な生活を送り、便利さと豊かさを手に入れました。
けれども、その豊かさの中で、私たちは何かを失っているのかもしれません。
子どもの頃から、道端に生える植物を「雑草」と呼ぶのが当たり前でした。
人によっては、見た目を整えるために除草剤を撒き、草を枯らします。
しかし、皆さんが「雑草」と呼ぶそれは、本当に雑草なのでしょうか?
私はかつて、そう思っていました。
けれど今は、草を「草」と呼ぶようになりました。
正直、名前を知っている草はほんの一握り。
それでも、「雑草」という言葉が少し乱暴に思えてきたのです。
目次
第1章|コンクリートの時代と自然との距離
住宅が立ち並び、日本では西洋の文化が取り入れられ始めました。
それに伴い、コンクリートで舗装された街並みが増え、自然と人との距離は年々遠ざかっています。
🧾 出典:国土交通省「都市緑地の現状」(2023年)によると、日本の都市部の地表面の約70%が建物や舗装で覆われており、緑地率は減少傾向にあります。
自然との共生はどんどん難しくなっているように感じます。
そして、舗装された場所が増えるほど、ゴミのポイ捨ても目立つようになりました。
最近では田舎でも不法投棄が増えており、静かな環境が少しずつ変わってきています。
第2章|「花を植える」ことでゴミを減らす取り組み
全国には、「花を植えることでゴミを減らす」活動もあります。
地域の人が花壇を整備することで、美観が保たれ、ポイ捨てが減るという報告もあります。
🧾 出典:環境省「美しいまちづくり支援事業」(2021)では、「花いっぱい運動」によってゴミのポイ捨てが減少した事例(富山市・福山市など)が紹介されています。
地域によっては、「整備しなければゴミが増える」という現実もあります。
つまり、人と草との“ちょうどよい距離”を見つけることが大切なのかもしれません。
第3章|草が支える土の力
草には、私たちが思っている以上に大きな役割があります。
草は土壌を豊かにし、微生物の活動を支える存在です。
草を抜くと、植物は“次の世代を残すため”に勢いを増して生長します。
そのため、完全に除去しても、しばらくすれば元に戻ります。
私は、草を「高刈り」するようにしています。
地表の近くで切ることで、根が残り、土壌の菌が活発になるそうです。
🧾 出典:農研機構「雑草と土壌微生物の関係」(2019)では、草の根が微生物の住処となり、有機物分解や土の団粒構造の維持に寄与すると報告されています。
草は、単なる「邪魔な植物」ではなく、土を生かす“呼吸装置”なのかもしれません。
第4章|草があることで守られる環境
草があると、地表が乾燥しにくくなり、水が土に染み込みやすくなります。
逆に、草を抜いた場所はひび割れが起き、雨水が浸透せず大きな水たまりになります。
🧾 出典:国立環境研究所「緑地の雨水浸透機能に関する研究」(2020)では、草地の雨水浸透率は裸地の約5倍と報告されています。
また、アスファルトで覆われた地面は、夏場に高温になります。
草地に比べて15〜20℃も高いことがあり、これがヒートアイランド現象の一因です。
🧾 出典:環境省「ヒートアイランド対策ガイドライン」(2023)より、アスファルト面は草地よりも平均約17℃高温。
草をすべて取り除くことは、涼しさや水の循環を失うことでもあります。
第5章|草と人の共生をもう一度考える
草は、抜いても刈ってもまた生えてきます。
根絶するのは難しく、完全な“敵”にすることは現実的ではありません。
それよりも、草がもたらす役割に目を向けてみると、
地表温度を下げ、土壌環境を守るなど、私たちにとっての“味方”でもあるのです。
一度立ち止まって、身の回りを見渡してみてください。
あなたの暮らしのすぐそばで、草たちは確かに息づいています。
🪴まとめ
「雑草」という言葉には、“不要なもの”というニュアンスが含まれています。
けれど、草は決して不要ではありません。
むしろ、環境を支え、命を循環させる大切な存在です。
もう一度問いかけてみたい。
――草は本当に雑草なのか?
あなたの足もとにある“草たち”を、少しだけ見つめ直してみてください。
Thank you for reading this blog, everyone 🙂